カテゴリー
営業日のご案内
最新情報
ホーム >>
お祭りとお囃子(篠笛・横笛)

日本には、約7万のお寺と約8万の神社があり、1年間に約4万もの祭りがあります。
お祭りでお囃子を聞いて、篠笛(横笛)の興味を持ったという方も多いのではないでしょうか。
祭りにお囃子はなくてはならないものであり、お囃子がお祭りを何倍も楽しくしてくれるといっても過言ではありません。
一口に祭りの囃子といっても、屋台・山車囃子、舞殿や居囃子の囃子、神幸祭の囃子、獅子舞囃子などいろいろあり、
また、同じ屋台・山車囃子でも多くの種類の囃子や曲目があります。
祭りごと、屋台・山車ごと、連ごとにそれぞれ由緒と伝統があり、独特の旋律とリズムを持った囃子が作られています。
お祭り囃子では笛の合図で演奏を始めることが多いため、笛の奏者は、囃子全体の盛り上がりを左右する重要な位置にあります。
また楽譜(数字譜)は一部の曲にしかなく、口伝によるものが多いため、伝承者がいないところでは絶えつつあります。
|
(全国各地の有名なお祭りの例)
青森「ねぶた祭り」
仙台「七夕祭り」
東京「三社祭り」「神田祭」「山王まつり」
埼玉「秩父夜祭り」
岐阜「高山祭り」
愛知「はだか祭り」
京都「祇園祭り」
岸和田「だんじり祭り」
徳島「阿波踊り」
博多「どんたく祭り」
|
 |
お祭り用品
お祭りに必要に笛や、祭り衣装など下記からご購入できます。
お祭り囃子に使用する笛
※以下はあくまで目安です。お使いになる笛は必ずお確かめください。
・江戸囃子・・・・・六本調子~六本半調子古典調(江戸篠笛)
粋を聴かせる江戸囃子では短めの六笨半調子が主流です。
・江戸里神楽、寿獅子・・六本調子~六本半調子古典調(江戸篠笛)
江戸囃子と同様に江戸物には六笨や六笨半調子がピッタリです。
・祭り囃子・・・・・五本調子~六本調子古典調
地域によっては三本調子や四本調子を使うところもありますが、
関東の地囃子では圧倒的に五本調子が多いです。
五本調子を使用する囃子連では、六本調子は子どもの練習用として使われます。
五本調子を使用する囃子連では、六本調子は子どもの練習用として使われます。
・獅子舞囃子・・・・六孔獅子笛
獅子笛の基本は六孔で、地域性が強いのが特徴です。
六本調子から八本調子が多いですが、保存会などで実際に使われている笛を見本として、
その通りに彫るのが原則です。
・祭り笛
阿波踊り・・・・六本調子~八本調子ドレミ管又はみさと式篠笛Bb管~C管
阿波踊りでは各連によって調子が変わりますが、六本調子か七本調子が多いようです。
裏穴のある、みさと式篠笛を使う所もあります。
秩父屋台囃子・・・一本調子~三本調子古典調
秩父夜祭りで使われる笛は昔は一本調子でしたが、今は三本調子が多いようです。
山車囃子・・・・・四本調子~六本調子古典調
地域によってまちまちですが、四本から六本調子が多いです。特殊な飾り金具を付けたりする場合もあります。
『古典調(お囃子笛)って何?』
指穴の大きさと間隔がほぼ均等に作られた伝統的なお祭笛です。
音階には西洋音階に調律されていません。(他分野の邦楽曲、洋楽曲の演奏は困難です)
伝統的な祭囃子、神楽、獅子舞などの郷土芸能に多く用いられています。
指穴の数は「六穴」や「七穴」など地域によって違います。
籐や漆で装飾した笛もあります。
どのタイプの笛を購入すればよいかは、地元の祭囃子保存会・教室・先生に 御問い合わせください。
※その他、笛については篠笛Q&Aをご覧ください。
『お祭り・お囃子に参加したいけれど、始め方が分からない・・・』
そんな方は、まず地元の神社やお寺に聞いてみるのも手です。
地元でお囃子の連(グループ)があり、参加者を募集しているかもしれません。
お祭りで使用する笛も地域によって様々です。
多くの場合は古典調(囃子用)笛と呼ばれる笛を使用しますが、地域によって異なります。
笛をお探しの場合は下記を確認してください。
●用途・種類:「古典調(囃子用)」か「唄用(ドレミ調)」
●調子:「?本調子」の数字
●指穴の数:「七穴」か「六穴」
© 2025 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved

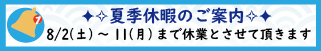
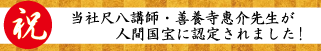







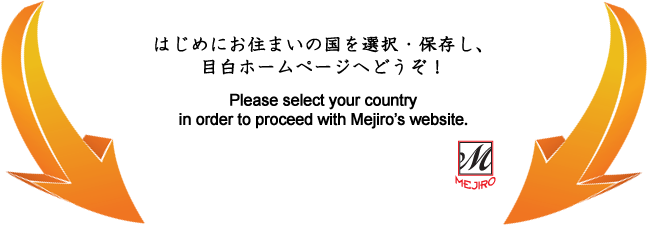

.jpg)